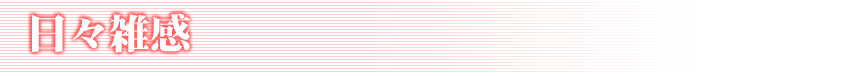 |
 |
| 浅草の浅草寺は外国人でいっぱいだ。初詣などは、日本人よりも多く、参拝に並ぶ行列からは、さまざまのアジアの言語が聞こえてくる。外国人は「安い、安い」と喜び、円安で伝統ある東京滞在を楽しむ。
他方で、虎ノ門ヒルズや麻布台ヒルズが新たに登場し、高さを競うタワマンもニョキニョキ立って、コンクリートの城が東京の勢い止まずの印象をもたらしている。集まる人々が、あるいは巨大な城が、誇るのは、終戦後から復興を続けた東京という努力の街だ。
しかし、待てよ。日本が劣化しているのと同様、東京にも劣化が既に始まっている。南海トラフ大地震が襲ったら、北朝鮮のミサイルが降ってきたら、どこに逃げるのだ。神宮の森や皇居やいくつかの候補地はある。だが、都が防災・防衛の具体策を人々に伝えているだろうか。否、である。
マンションの価格が平均1億円を超えた首都で、買えるのは、日本人ではない。武田薬品の外国人社長の年収は15億だそうだが、先端のITやバイオからとり残された従来型の中小の社長は、一連の賃上げ圧力にすら応えることはできない。
幼少時から巻き込まれた受験戦争の果て、一流大学を出ても、夢見るは外資系企業。官僚は消極的選択、政治家は選挙での一発目当てばかりで、永田町と霞が関は無能の集団、活気から取り残されている。
東京をどうするのかを問うのが都知事選ではないのか。経済的にも、物理的にも、安心、安全の街をどう築くのかが争点ではないのか。若者の夢を育む政策が最も求められているのが東京ではないのか。
少子化政策にマイナーであり医学的にも問題がある無痛分娩の補助を唄う小池さん。相変わらず何を言っているのか不明で、ただ眉間にしわを寄せて「何でも反対、私は挑戦する」の蓮舫さん。実践的には聊かましだが、どこまで追い上げられるかの石丸さん。都民の思いとずれてはいないか。
都知事選が終われば、岸田おろしが始まり、意外性のない「やっぱりそうか」の総理が出てきて、海図なき日本の運営が続けられることだろう。失われた東京、失われた日本の始まりが2024年である。 |
| 過日、白山義久京大名誉教授のお話を聞く機会を得た。題は「国家管轄権外区域の海洋生物多様性(BBNJ)の保全及び持続可能な利用に関する新協定」についてである。
耳慣れない題であるが、簡単に言うと、公海の資源保全の協定ということだろう。国連が音頭を取り、23年6月に正式に採択され、60か国が批准してから発効される。日本はまだ、署名も批准も検討中である。シンガポールや環境政策重視のドイツが先導役を務める。
これまで海洋法については、領土の沿岸に当たる領海や排他的経済水域が定められ、生物多様性条約において、沿岸国による管理が規定されている。しかし、公海については何も定めがなかった。
日本は、途上国が公海での生物多様性は人類共通の財産であると主張するのに対し、共通財産は海底鉱物資源に限るとしている。また、公海でのモニタリングには膨大な費用が掛かることを懸念する。しかし、海洋国家日本がいずれ署名・批准することは容易に予想される。海洋遺伝資源から医薬品の開発などの便益が得られることも分かっているのである。条約締結国のコスト負担や便益の配分などの検討が急がれる。
何よりも公海という未知のフロンティアが存在していたことに驚く。宇宙開発については既に1967年に宇宙条約ができていて、昨今では、アメリカのみならず競争して宇宙のフロンティアに向かう国々が増えた。一方で人口爆発を憂慮し、他方で人類が使える未開発の資源や新たに住める惑星などがあるとしたら、フロンティアに向かわない手はない。
これまでも、各国が協力し、あるいは競って南極調査を行ってきたが、公海に眠る便益を各国合意の下に、日本が積極的に求めていくことは望ましい。資源がなく人口減少の国日本は、国益として取り組むべきである。日本は、従来、科学が導くフロンティアに関し、政治が消極的だった。洋上風力発電も、CCS(二酸化炭素分離貯蔵技術)も、宇宙太陽光発電も、国際リニアコライダーも、学術者からのアイディアに政治が積極的に乗り出すことはなかった。
下り坂の日本と言われているのを甘受せず、国益のために、公海にでも、新しいフロンティアにでも、出て行って勝負する日本でありたい。検討倒れと遅延はやめてほしい。 |
| 衆議院補欠選挙が迫っている。総選挙の前哨戦と呼ばれるが、否、結果は既に明らかである。自民党は負ける。
そこで、岸田首相の破れかぶれ解散につながるとの見方が強い。岸田首相は、国政よりも自民党よりも、自らの保身を優先する。総裁選前に総選挙ができなければ総裁を続けること自体が難しいのだ。
自民党が少しでも有利に戦おうとするなら、党首を替えるしかない。どこかにダークホースはいないのか。安部派つぶしにとどまらず、伝統のリベラルを捨てた宏池会、またぞろ世襲にこだわる二階派、トランプに尻尾を振りに行ったオッチョコチョイの麻生派を「ぶっ壊してやる」と勢いよく出てくるダークホースもいないとしたら、自民党の人材払底も甚だしい。
そのダークホースにならんとした小池百合子は東京15区からの出馬をあきらめ国政復帰を見送った。それもそのはず、再燃した学歴詐称が今回ばかりは握り潰すことができない。偽の卒業証明というエジプトからの恩を買った小池は、他国エジプトのエージェントであり、国政に出ることは憚られる。政治家として都知事に留まることも許されない。
それにしても、自民の逆風を自らの順風に置き換えられない野党のだらしなさも目立つ。もし政権交代を勝ち取りたいなら、野党もまた党首を替えるべきである。立民は、無学無策のアイドル党首に、極左的女性議員が取り巻き、バックには民主党崩壊の罪人たる顧問が大勢いる。
最近、米山隆一議員の舌をまく質疑の雄弁さが報道されている。岸田首相は照準のぼけた答弁をひたすら読み、松本総務大臣はしどろもどろの答弁。なんだ、立民にもまともな議員がいるではないか。石橋湛山の小日本主義を唱える篠原孝など、腐りかけた幹部の背後にまともな議員も少しはいる。世の中の賛同を狙うなら、野党も党首を替えよ。替えねば、誰も政権交代を望まない。自民・維新連立の方がまだましだ。
米国大統領選挙もおじいさん同士の戦いで気の毒だが、このままいくと、日本は腐ったもの同士の戦いになり、もっと気の毒な状況になるだけだ。
|
| アメリカ、ロシアを追いかけて、中国、インドも宇宙開発競争に参加している。日本も技術の国の面目をかけて負けじと、最近のH3ロケット打ち上げ成功や小惑星探査機はやぶさの活躍等、人々に知られるようになった。宇宙産業への投資が2030年には倍増すると言われているが、いかんせん、日本の予算は少なく、民間の参入が限られてもいる。
宇宙は人類にとって未知の代表だ。しかし、地球上にも未知はたくさんある。南極だって、深海だって未知だらけだ。人間社会に注目すれば、日本にとって最も未知な国々はアフリカではないだろうか。近日、多谷千香子法大名誉教授のアフリカ・マリ共和国のお話を聞く機会を得たが、先生は「日本で、マリ共和国って南米の国ですかと質問された」と苦笑していた。
筆者もそのたぐいだ。半世紀も前に「マリ共和国の花嫁」なる本を読んで、マリに嫁いだ日本人女性の「珍妙」余りある経験を大声で笑いながら読んだくらいだ。マリ共和国は、戦後、フランスから独立し、民主主義国として存在するものの、リビア内戦をきっかけにイスラミストの流入によって、今、国分裂の危機にあるという。
筆者の関心は戦況や政治の情勢にあるのではない。社会政策を業として実践してきた筆者は、日本にとって、将来の人材導入をアフリカに求める可能性を探りたい。日本はもちろんのこと、先進国は少子化で人口減少を余儀なくされ、南米や東南アジアなど中進国も少子化現象が始まっている。
日本が実質的に移民労働力として扱っている技能実習生は年38万人入国しているので、日本は世界4位の移民大国にである。技能実習制度は廃止する方向だが、形を変えて維持しなければ日本は人口減少に耐えられない。この制度ではかつて中国人が入ってきたが、中国本土での経済発展により来なくなった。今は、ベトナムやネパールが多いが、円安の影響で、日本で働くうまみが大幅に減少し、やがてアジアの国々からの人材獲得も難しくなりそうだ。
そういう状況の中で、アフリカだけがすべての国がたどる人口現象と異なり、人口を増やす一方である。要因には複数婚、一夫多妻制の社会であることが挙げられるが、アフリカは、天然資源とともに人材の宝庫にもなろう。日本は、アフリカの豊かな資源獲得に、欧米や中国の後塵を拝しているが、人的資源の獲得は、いち早く人口減少が始まった国として、着手を遅らせてはならない。
アフリカは欧州が競って植民地化したが、マリ共和国を含むサヘル地域のように特にフランス植民地圏は低開発国にとどまっている。アングロサクソン系は少なくともインドで鉄道、学校、官僚制度などのインフラ整備を行った例もあるが、アフリカのフランス、南米のスペインなどのラテン系は搾取だけに執心した感がある。現在においても、マリ共和国はフランスの介入失敗で、ますます情勢は悪化していると言う。
日本は、人口減少という必要性から、植民地時代からの歴史や責任を持つ欧州に対抗して、アフリカになにがしかの貢献ができる時が来た。宇宙よりももっと身近な未知アフリカへの挑戦を促したい。 |
 | | [2024/02/19] | | 政治に絶望しつつも、イノベーションを |
|  |
| 政治とカネでニュースが埋まり、自民党の不支持率が86%に及ぶ(テレビ朝日)事態に至った。そのさなか、JAXAのH3ロケットが打ち上げに成功した。約一年前、打ち上げの失敗を泣きべそをかきながら会見していた責任者の顔がほころんでいた。
日本の科学や経済政策の遅れが国際的に認識されているときに、H3ロケット打ち上げ成功は快挙である。日本はまだやれる科学の力が残っていることを示してくれたのだ。日本は、近年、とかく遅れや停滞が指摘されてきた。太陽光発電、電気自動車、コロナワクチンの開発、AIの普及などで遅れが目立ち、先進国の顔を失いつつある。
しかも今の政治のカオスと一人当たりGDP32位(IMF)の経済力の低下は、日本を先進国における悪玉の存在にしている。先ずは、政治の刷新は必須だ。リクルート事件以上の政治の腐敗は、与党自民党ではもたないことが明らかだ。では、誰が政権を担うのか。
政権交代を軽々しく言えないのは、自民党の体たらくは明らかとしても、それを責めるだけで、野党側にいかなる政治を行っていくかが見えないからである。日本再生のための政策はあるのか。H3ロケットに続いて、日本が技術的に優位にある浮上式風力発電や潮流発電を大々的に取り入れるのか。イノベーションを遮る学究体制を改める気はあるのか。
無論、それ以上に、国民が十分な生活費を手にし、消費を刺激し、二極化した階層社会の緩和が必要だろう。しかし、それは、イノベーションと同時にやっていかねばならない。決して、イノベーションを後回しにしてはならない。なぜなら、国民の消費意欲とイノベーションは日本再生の両輪だからだ。
自民党がモラルの欠けた人材だらけであるのに対し、野党は政策を打ち出す能力に欠けるアンチプロフェッショナルの集団だ。筆者は旧民主党に身を置いた経験から、このことは痛感している。
海洋工学の木下健東大名誉教授は、潮流発電を地域ごとのリーダーの下で実働部隊(共同体)をつくり推進すべきであると提言される。筆者が思うに、プロジェクトに政治家が絡めばまたぞろ利権争いになるだけで、地域のリーダーが金集めから、工学的知見から、全てを統括して行うべきである。木下先生曰く、その共同体は国家のようなゲゼルシャフトではなく、郷土の発展を願うゲマインシャフトの集団であることを目指す。
もう政治には任せられない。選挙に選んでもらうための「得か損か」だけのメルクマールを持つ政党(ゲゼルシャフト)を否定し、郷土を、そして日本を再生させる意欲に燃えたゲマインシャフトの共同体を新たなイノベーションの担い手として盛り上げていくべきだろう。
|
| 過日、シム チュン・キャット昭和女子大教授のシンガポール教育制度についての講義を聴く機会を得た。東京23区ほどの広さで、人口6百万弱の国が、一人当たりGDP世界5位(23年 日本34位)、国際学力調査で世界一の座を獲得するシンガポールの底力はどこにあるのか、不作の30年を送ってきた日本にとって、大いに興味をそそられる。日本はかつて経済・教育指標において今のシンガポールの地位を占めていたことを考えると、下降原因を探るにも、シンガポールから学ばねばならない。
シンガポールは、原則公教育の国であり、ナショナルカリキュラムの下で教育が施される。先ず、多民族国家であり、民族言語を教育に取り入れつつも、殆どの教科は英語で行われる。英国支配の国であったから、教師に事欠くことはなかったろう。その上で、義務教育6年を修了すると、大学進学予定コースと職業教育コースに振り分けられ、ドイツの制度が取り入れられている。
職業教育コースでは中等教育の後、美容師、パテシェ、栄養士、保育士等の資格教育が公教育の下で行われる。大学コースも含め、どのコースも親の所得に応じ、日米などと比較すると授業料が低廉に押さえられている。コースの変更も成績によって可能であり、教育は複線化している。公教育によって、食いっぱくれる若者はいない制度である。
翻って、日本の教育はどうか。高校はかつての農業、工業、商業などの職業教育が少なくなり、普通科が7割になって、結果的に6割の若者が大学に行く。教育制度は単線化している。そもそもは戦後の米占領政策によって六三三四制が創られ、その結果、旧制高等、帝大時代の教育年限を下回り、高等教育は低迷することになった。同時に、大学の大衆化が進み、偏差値による格差階層社会は結果的にできたものの、エリート教育はほぼなくなったと言える。一番の犠牲は研究力の低下だ。
その大学は概念教育から脱しきれずキャリア教育に欠け、大衆大学に入るために受験に有利な私立勢の台頭もあって公教育は低迷するばかりである。各地教育委員会ごとの独自性は見られず、文科省の方針をなぞる教育、それはゆとり教育が行われたり廃止されたりのダッチロール政策と付き合っていく姿に表れている。
シンガポールでは教員の給与レベルは極めて高い。校長は高学歴で高額所得者であり、教員の採用から予算の配分まで任されている。つまり、教育者であると同時に経営者としての質を保たねばならない。日本の文教政策では見られない体制だろう。教職が経済的にも社会的にも高い地位を得る職業であることは、日本でも採り入れるべきだ。
低学力の子供には、教員の数を増やし、丁寧な教育が行われている。授業料は低く、子供は生まれ落ちたときから経済措置が行われ、塾に行く必要のない徹底した公教育を施しているという。しかし、全てがうまくいくわけではないだろう。両親が英語を十分に使えない家庭の子供は学力が低迷しがちであるし、精神を病む子供もいて、学力を誇るシンガポール教育にとって悩みの種である。
筆者が20年ほど前、オーストラリア在住中に会ったシンガポール人は、エリート意識がプンプンする人も多かった。日本人は英語が下手で、大学院教育を受けていない場合が多いが、シンガポール人は上からの目線で見てしまう傾向がある。リークアンユーは開発独裁という手法で、一寒村を世界のエリート国に生まれ変わらせたが、そこにも問題が潜むことは否めない。しかし、それでもなお、日本の30年に渡る経済と教育の低迷を救うのは、シンガポール方式ではないかと筆者は思う。
|
| 世界情勢のカオス、日本政治のカオスの渦中で迎えた元旦に、能登半島を震源とする大地震が起きた。被災者を慮りつつ、激動の年到来の予感がする。
年末、政界の生き字引こと平野貞夫元参議院議員の登場するユーチューブで面白い情報を得た。今回のキックバック問題について、検察は過去の過ちを悔いて、徹底的に取り組む姿勢であると言う。
過去の過ちとは、二階堂俊博元幹事長と野田佳彦元総理の金銭に関わる疑惑について、検察は政治に忖度して立件を放棄した件であると平野氏は言う。野田氏は当時財務大臣であり、財務省が大臣を守護したそうである。
筆者は真偽を分析する材料を持たないが、野田氏が社会保障と税の一体改革で消費税引き上げに拘ったのは、財務省に大きな借りがあったからではないかと考えて不思議はあるまい。
政治が個人の事情で行われるようになったのは、政治家自身が組織人になったり、資格や技術を持つ職業に就いたりしたことがなく、専ら選挙攻略の修練か世襲によって議席を獲得してきたからに他ならない。その経歴から、人のための政治が出てくる可能性はない。自らの損得だけがメルクマールなのである。
検察に頑張ってもらいたいが、与野党含めすそ野の広い政治屋の集団をそっくり変えるには、新たな政治集団が必要だ。まだ国民は投票先が見つからずにいるのだから。
2024年は、世界では停戦、日本では新党の出番だ。 |
| 共働き世帯と専業主婦世帯がニ対一になった今、専業主婦を前提としたPTAや子供会などの地域活動が成り立たなくなり、やめるところも増えてきた。また、公民館を中心とする趣味の会などはお年寄りの集まりでしかなく、地域全体を巻き込む祭りなどはできなくなったところが多い。
2015年のいわゆる増田リポートで謳われた「地方消滅」は推計や提言に批判が多いものの、地域のアイデンティティや地域文化という観点からは、現実化していると言える。人口維持も難しい中、文化的観点から、公民館活動やネットワークづくりを政策的に行っても、もはや焼け石に水としか捉えられない。
これは歴史の流れの必然である。かつての農村では、農作業を協働し、共に豊穣を祝う祭りをし、隣近所との物々交換やサービスの交換は必要欠くべからざるものであった。しかし、現在では、農家の一軒一軒が自分のトラクターを持ち、進んだ資本主義の下では、原則として、必要な財・サービスは市場で売買する。
賢い市町村が例えば子育て支援に力点を置いて移動人口を集めても、人口減少が前提の日本全体から見れば椅子取り合戦であり、政策不作の市町村は限界集落が進む。究極は就業機会の大きい大都市圏に人口は移動し、田園地帯の過疎化は避けられない。
もう地域活性化政策はやめたらどうか。半導体工場の建設で新たな街ができるというような経済的理由があれば別だが、単なるノスタルジアで地域おこしをやっても成功は覚束ない。他地域から人を借りて祭りをやっても、その地域の祭りの独自の意味は失われる。日本全体の市場を使って、人の移動と財・サービスの獲得を任せるしかあるまい。
90年代の橋本龍太郎政権に始まり、小泉純一郎政権によって増幅された市場原理化、徹底した資本主義化は当然に地域を壊したのである。人間関係で地域に守られて生きる時代は終わった。共同体のアイデンティティを共有して生きがいを感じる時代は終わった。今は、すべて市場でモノやサービスを求めなければならない。だから、皆が十分な財布を持たねばならない。
岸田政権の当初の目論見は、成長と分配の好循環をもたらす新しい資本主義の実現ではなかったか。人々の懐を温かくし、有償となった「地域の便益」を皆が買える社会にするのではなかったか。政治とカネの泥沼を脱し、原点に立ち返って仕事をせよ、岸田首相。 |
| 政治の世界はまさにカオスである。政策の不作に加え、政治とカネの酷すぎる状況。結論を急げば、自民党が分裂し、まともな政治が行える集団が新たな政治をリードしていく以外の選択はあるまい。そして、もう一つ提言したいことがある。
政治のカオスの背景には、もっとスケールのでかい人類のカオスがある。気候変動、海洋酸性化、金属汚染、アンモニア、そして人間の考える力である。これは過日、川幡穂高早大特任教授のお話で諭された内容である。人類の抱えるカオスの全体知に迫るお話であった。
全体知という言葉は寺島実郎多摩大学長がよく使う言葉で、一つ一つの情報を全体として捉えることによって世界を理解するための認識である。上記五つのカオスは全て人間が生み出した結果であり、川幡先生によれば、人間が引き起こした現象が顕在化した地質時代を「人新世」と呼ぶことが始まっている。その開始は1950年という。
20世紀初頭、コンクリート等から成る人工物の総量は生物の総量の3%を占めるのだそうだ。人間のなせる業のすごさである。地球温暖化の原因が二酸化炭素であることは科学的に証明され、気候変動のカオスを引き起こす。我々は既に多くの異常気象を経験している。二酸化炭素は海洋酸性化のカオスも引き起こし、炭酸塩が溶けて既に貝やサンゴ礁、食物連鎖上位の魚類に影響が出ている。
そのためにカーボンニュートラルの政策が流行り、二酸化炭素を抑制する電気自動車や太陽光発電が推進されるが、リチウムやアルミなどの需要が高騰し、電気社会は有害物質を排出すると先生は言う。これが金属汚染のカオスである。
アンモニアは約8割が肥料用に使われるが、アジアの電源に多い石炭火力発電でアンモニア燃料を混ぜて使うと二酸化炭素排出が減らせる。アンモニアを肥料に使うのか燃料に使うのか、取り合いになるのがアンモニア・カオスであると先生は指摘。アンモニアの化学肥料なかりせば世界人口は半分だったとの試算もある。
さて、最後に、川幡先生のお話の「オチ」は、人間の考える力のカオスである。AIの発展により、人間はAIに飼い慣らされ、頭脳が縮小するとのことである。犬も猫も野生のオオカミやヤマネコに比較すると、頭脳は6割程度に縮小している。人間に飼い慣らされ、野生で生きる術を失ったからである。人間に迫る「考える力のカオス」は戯言ではない。
カオスの渦中にあるにも拘わらず、学問も職業モラルも身に着けない政治家カオスを一掃するのは、科学者の力であり、政治家の背中に「二酸化炭素」のレッテルを貼って追放する役割を果たしてほしい。 |
| 伊藤美奈子奈良女子大教授のお話を聴く機会を得た。先生は臨床心理学の専門で、スクールカウンセラーとして現場も擁している。子供の自殺予防について熱っぽく語った。
キーワードは、中学生が危ない時期であると筆者は捉えた。いわゆる思春期であり、第二次性徴の訪れにより身体の変化が現れるとともに、自己意識が高まりアイデンティティを模索する時期である。中学生は、調査の数値上、小学生と比較して自己肯定感が低下し、小学生・高校生に比べ、最も「死を恐れぬ」感覚を持つ。
性衝動を含むとんでもない行動に走る可能性があり、親や大人の上からの小言・助言を拒否する傾向にあり、その不安定状態が心身ともに大人になるまで続く。中学生がその出発点であり、かつ最も不安定であるから、衝動的な死の選択を抑止するカウンセリング、また制度的な支えが必要である。
子供たちは、デジタルネイティブであるが、相談相手としては、ネットでの相談窓口よりも友達を筆頭に「生身の人間」を選ぶ。そもそも相談しないとの選択も多い。死の選択や自傷行為を抑制するには、周囲の人間が子供たちの心を察し、対処してやらねばならないのである。
大人はそれぞれが中学時代を思い出し、「何であんなことをやったのだろう。何で親に反抗したのだろう」と振り返るにも拘わらず、いつまでも子供を上からの立場で観て、抑圧者になってしまうことが多い。先ずはそれを反省すべきだ。
子供の自殺は増えているが、そこまで極端な選択をしないまでも、将来、折角の就活で得た職業も長続きせず、引きこもりが長引く、結婚願望がない等現代の若者が抱える問題の「芽」が中学生の時期に発生するのである。大人は真剣に中学生に向き合わねばならないはずだ。
伊藤先生は子供の自殺予防の立場から「死を正しく畏れる」ことを教えなければならないと主張する。かつてに比べ身近に死を体験する子供が減ったことも要因であるが、死を安易に美化することを戒めねばならない。
筆者は、子供の発達全般に関しては、「生は、未来は、正しく楽しむ」ことを教えねばならないと考える。経済成長しない日本、格差広がる社会で閉塞感に捕らわれている中学生を始め子供たちに「生を正しく楽しむ」ことを教えられるか。
それは、社会の責任であり、政治の中心の課題だろう。 |
|
 |
|
  
|
|
|
|
|
|
|